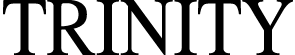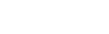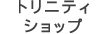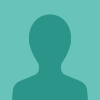狼語り……神の使いである『眷族』のお手並み拝見
狼眷族のグラウは稲荷眷族の甚六狐に呼ばれた道すがら呑気に迷い子の猫霊を連れて来たが、遠目に見えてきた甚六の祠には黒いもやがかかっている。
良くない霊が居ると空気は冷えて見た目に黒く薄暗くなる。猫に怖い思いをさせたくない。
その頃、祠の稲荷眷族の甚六は舗装された道を(この辺に舗装されて無い道なんて無いが)灰色の狼と虎縞模様の仔猫が祠に向かうのを見つけ、からかいがてら迎えに出た。
「遅いなあ。しかもコブ付きかぁ。グラさんの子かい? 」
甚六の戯けた感じの質問を、無断で連れを伴った側のグラウは『まあな』という表情の苦笑いで受け流す。彼等は風呂屋の手前、路地一つ分の辺りで落ち合い、祠へ向かう。
この時甚六は普通の狐の姿をしていた。グラウとはからかいあえるほど親しい。茶化すような文言は今みたいに甚六から言う。グラウは甚六の様子から、薄暗いものが然程凶悪なものではなかろうと安堵し、仔猫連れの言い訳をした。
「仔猫の事かい。ほんのさっき見つけたんだ。連れてきたには理由がある。ただの猫じゃなさそうなんだ。額に神紋があった痕がある。」
グラウが挨拶するよう優しく鼻先で虎縞猫の小さな背を押すと、怯えも知らぬ様子で素直に甚六の前に押し出された。
甚六が猫の顔を覗き込むと猫の額の中央に薄く紋らしき光る模様がある。
「元は誰かの使いか眷族か。何か敵対する者の術で攻撃されて封じられてたのだね。」
一瞬だけ甚六の毛色が銀色に成り尾が六つの姿になった。甚六もグラウも少し本気で魂の力を使うと少し本来の姿が現れる。
「甚六狐様。はじめまして。気がついたら本当の名前や自分の事が思い出せなくて、こまっていたらグラウさんが連れて来てくれました。今日グラウさんとする事を見学させてください。」
仔猫は緊張して事前に道すがらグラウに教えられたセリフより長々した挨拶をした。
「いいよ。あと、わたしを呼ぶのは『様』でなくて『さん』でいい。ロクさんでもいい。グラウもグラさんでいいよな。」
甚六は途中で猫からグラウに会話の相手を変えた。複数の相手が居る時の甚六の話し癖の一つだ。グラウは『ほらね』といった風体で猫を見る。猫は受け答える余裕はなさそうで速歩きで付いて来る。
三匹が祠まで来ると、暗い靄(もや)に包まれて、甚六の部下たちが異形な物たちを押さえ込んでいた。
「それでだ、あれなんだが、見た目で分けておいたがどう片付ける? 」
甚六は化け物を見向きもせずにグラウに仕事を振る。グラウは過去にあった出来事の因縁因果を探し、視覚にして甚六たちの魂に投影する。
元が何か、どうしてこうなったかを視る事で、霊の正体とゆく先を見分ける助けになる力を使うのがグラウだ。