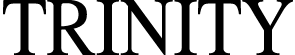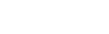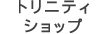・薬効を表す「味」
インド生活を始めて間もない頃(かれこれ19年前の話です)、目の前に出てくる料理という料理のほとんどすべてが、激甘、激辛、激塩辛、のオンパレードで、当時の私は、インド人の味覚はまじめに壊れていると本気で思っていました。
醤油や味噌といったアミノ酸ベースの繊細な味付けを大事にする日本伝統の食文化の中で生まれ育った私のような日本人にとっては、インド料理の味付けが雑に感じることは、ある意味しかたがないことだったのかもしれません。(ちなみに日本にあるインド料理レストランのほとんどは、日本人の舌に合うように、かなりマイルドな味付けに作られているのが普通なので、実際のインド現地の料理とは大違いです)
しかし、インド料理の味の濃さには、アーユルヴェーダ発祥地ならではの、科学的で明確な理由があったと今では思います。
それを一言でいうならば、アーユルヴェーダの世界においては、「味」自体が「薬」だからです。
……これは一体どういうことなのでしょうか?
今回は、そのあたりのことについて、お伝えしたいと思います。
***
私たちは普段、食事をとるときというのは、ほとんどの場合、その食べ物がおいしいかおいしくないか、つまりはその味自体を楽しむために食べる場合がほとんどで、その味自体を「薬」と思うことはほとんどありません。
ですが、アーユルヴェーダの世界では、食べ物、特にハーブに対し、そのハーブが持つ味、要素、熱する効果なのか冷却する効果なのか、またそれを食べた後の消化後の効果、その他さまざまな効能を考慮することがひとつの科学になっています。
そしてこの科学が、ハーブを理解するための主な要素となります。
この点では、中国の漢方ととてもよく似ています。
これは、西洋医学の、細部の迷路に迷い込んでしまいそうな化学分析の複雑さのオンパレードとは一線を画し、ハーブがもつ基本的な性質を明らかにした、とてもシンプルなエネルギー体系です。
ちなみに西洋の薬草学には、アーユルヴェーダや漢方のような、治療のために不可欠なハーブがもつエネルギー原理への理解がないため、ハーブを使う上では、西洋的な体系はどうしても不利になるともいわれています。
***
私たちは通常、味と治療効果を結びつけるという発想そのものがなく、味とはいわば、「舌の表面」の娯楽であり、楽しみの一種です。
ところがアーユルヴェーダでは、ハーブの味そのものが、決して偶然の産物などではなく、そのハーブの特性全体を表したものと考えられています。
そして、違う味のものからは、違う効果が得られます。