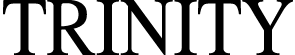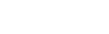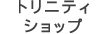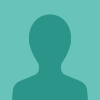稲荷狐の甚六はゆっくり話しはじめた。
「あの着物、思い出したんだ。将門さまは伯父たちから領地を奪われそうになって反撃して退けたたものの、伯父方の源護が朝廷に将門さまが《戦を仕掛け親族を惨殺した》と訴えた事があってね。
将門様は違う理由で都に行かれていたが、帰郷する。将門さまが護の訴えで呼び出され、寛明(ゆたあきら=朱雀天皇)さまの元服で罪を赦されたと誤解した伯父たちは、息子たちを失った源護の無念を将門さまの妻子の命を奪う事で同じ思いをさせようと企てた。
あの着物をさ、汚れたから洗うと言って側室に混じっていた間者(スパイ)の女が洗濯に出してすぐ、葦深い河原の船小屋で女子供総勢8人が、将門さまの伯父の平良兼の手下たちに襲われたんだ。
間者の女は返されるけど、あの桔梗柄の着物を着ていれば不思議な力に守られたたはずの奥方たちは、抱いていた赤児を含めて無残な姿で川に捨てられた。
お世話役の少女や側にいた猫たちもだ。
わたしは当時、京の都から父を気遣う正国さまの使いとして坂東へ戻ったばかりで、間に合わなかったのだよ。武蔵の国に居た薬葉さんも異変を感知し、通力を駆使して迅速に駆けつけたものの、間に合わず、息も絶え絶えな仔猫を見つけるのが精一杯だった。」
「薬葉さんが見つけた仔猫が『ちゃ』なんだね。」
グラウが問う。
「『ちゃ』の魂の姿は、仔猫のままだ。助からなかったって事か。」
グラウが一瞬銀色になった。感情が揺らいだのだ。
「思い出したんです、その日。」
ちゃは、いつもとはちがう鋼のような波動を放ちながら誰にとはなく悲しい記憶を語りだした。
「わたしはまだ兄弟姉妹たちと、じゃれあって、おなかがすいたら母の乳に競って食らいつくのが楽しい幸せな毎日をすごしていました。
その日、どうしてそこに居たのか当時はわかりませんでした。奥方さまたちとお付きの人たち、護衛のひとたち、まわりにいる人も、母をはじめとしておとなの猫も、なんとなくいつもと様子がちがいました。
いつでも船を出せるようにしながら、舟小屋で静かにしていました。後で知った事ですが、河のずっと向こうでは伯父たちが挙兵した情報を聞いた将門さまがそれを迎え撃つために兵を集めていて、奥方さまたちはここに隠れていたものでした。
しかしながら、密告者により、敵に居所は知れていたそうです。
昼頃、領民の荷物運びの船の荷に隠れて河を下ってきた敵兵数人が舟出し口から侵入してきて、兄弟は踏まれたり刀を刺され、わたしはつかまれて投げられたせいで舟小屋の板壁に叩きつけられて気を失ったようでした。
気が付くと辺りは血の匂いがして、護衛のおじさんたち、仲間の猫も動かなくなっていました。見える範囲に理解できたのはそれだけでした。
わたしの体は動くことができず、仰向けのまま、目と匂いだけで母を探しましたが見つかりません。
板壁の隙間からもれる光で、時間がほとんど過ぎていないことがわかりました。
体中痛いのに眠くて、目が自然に閉じてしまいそうになっていたら、まだ景色の見える目に、巫女装束の女の人が陽炎のようにぼんやりと見えてきて……。」