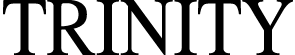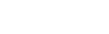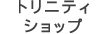命の大切さを教えてくれるもの
先日、パーマン大好き仲間の男性に面白い事を教えて貰いました。某有名学習帳から昆虫が消えていたってご存知でしたか?
僕は小学生と接する機会があまりないので気づかなかったのですが、自分とは縁がなさそうな文化も、もっともっと積極的に観察する必要があるなと反省しました。
もちろん学習帳メーカーを批判するつもりはありません。時代の流れなのでしょう。ノートの表紙から昆虫が消えた理由の詳細はわかりませんが彼に聞いた話によると「子供が怖がる(気持ち悪がる)から」とのことでした。
このエピソードを通して考えると、今の若者は命に対する尊厳や危機感が少々足りないのではないかと思っている人も多いと思いますが、それは学校教育や親の教育方針だけの問題ではなかったという仮説が立てられます。
ずばり、それは環境の変化です。参考までに僕は昭和生まれの人間です。子供の頃には野山で無くても昆虫はいました。池にはヤゴ(トンボの子供)やゲンゴロウがいました。水たまりにはアメンボウがいました。草むらにはバッタやコオロギもいました。クワガタやカブトムシは、流石に滅多に見かけなかったのでレアな昆虫ではありましたが、皆無という程ではありませんでした。
今は、モンスターを対戦させるゲームが若者の間で流行っているようですが僕世代以前の少年たちはゲームのキャラクターではなく、生身の昆虫を戦わせて遊んでいました。
昆虫は今でこそ商品(おそらく養殖)と化していますが、元々は違います。自然の中に生きている野性の存在だったのです。少年たちは、自分の頭と身体を使って昆虫採取をし、図鑑で調べ、飼育し、観察し、そして戦わせました(←わらうところ)
女性はもしかしたら「うわ!そんなのヤだ!気持ち悪い!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはものすごく大切な事なのです。
子供たちは昆虫を通して自然界のルールを学んでいたのです。まず、ゴキブリ以外は家には住んでいない。植物や水のあるところに生息していることを知ります。当然、昆虫を追いかけていると綺麗な場所にお上品に生活しているわけではありませんので、服も汚れますし泥だらけになります。しかし、それによって自然界の構造も何となく身体でわかってくるのです。
すると次第に食物連鎖や弱肉強食も教科書で学ぶのではなく自分の目で学び取ります。数値化された戦闘力ではなくアナログ的でリアルで生々しい生命の強さを知ります。そして、死の概念すらも昆虫から学び取ります。リセットボタンでやり直しができるわけではないことを知るのです。時には、アリを水辺に落としてみるなど子供特有の(?)残酷な行為もありますが、それらの経験を通して少年たちは命を学びとって成長して行ったのです。
戦わせて遊ぶのも実は残酷なのではないかと年齢と共に悟っていきます。ゲームのキャラクターであればリアルな死ではないので遠慮なく殺し合いが出来てしまうので、その辺に対しては無関心ですよね。痛みや悲しみなども、この辺の時代に経験として自然に学んで来たのです。そして、大人になるにつれ、それらの経験を人間社会にも当てはめて応用して行ったのです。
ちなみに僕はゲームを批判しているわけではありません。大学生頃までゲームばっかりやっていましたし、架空の世界を想い浮かべて想像力を逞しくしていく作業はとても楽しいひと時でした。
ただ、昆虫がいなくなり、野良犬も野良猫もいなくなり、日本からは自然がどんどん失われて来ました。小さな子どもは空き地や公園で遊ぶのではなく、転んでも痛くない床で、遊び道具がたくさんあるお店で遊びます。そして大きくなるとゲームで遊びます。怪我もしませんし、親の管理も楽です。ただし子供たちから野性が奪われてしまった事も事実です。命は何処でどうやって育まれ、生きるとはどれだけ大変でどれだけ尊いかを学ぶ機会を失ってしまったのです。
理科の教科書に昆虫が載っているかもしれませんが、それこそ実写のモンスターと思ってしまう子供もいるかもしれません。「なんで生存(存在)してないモノの生態系なんて学ぶんだろう?」なんて思うかもしれません。
21世紀はヴァーチャルとリアルが混在した時代です。僕もリアルな空間を生きてはいますが、こうして電子媒体(ヴァーチャル)を通して僕の存在を示し、語りかけています。それでも、僕はかろうじて昭和の子なので、リアルをよりリアルとして認識で来ているつもりです。
現代人が昆虫を気持ち悪いだけの存在と認識するようになってしまったのは、昆虫に対する免疫が無くなってしまったからだと思います。正直言えば、子供の頃は平気でしたが、今は自分自身も虫を触れません(←わらうところ)
僕たちは文明の発達とともに自然を破壊するだけでなく、人間自身の心身の成長する環境さえ自らの手で破壊してしまったのではないか。たまに、そんなふうに思えてくるのです。