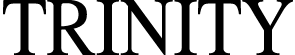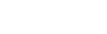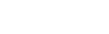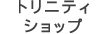愛知県田原市で無痛整体 あんしん堂 田原赤石院を開業している院長の河合出です。
今回からは五行(五臓)の運動、姿勢を取ることにより内蔵が動きどのような効果があるのかを紹介します。
これはもともと武術の練功法でしたが、誰でも簡単にできるように運動療法として改編したものです。
中国には陰陽五行説と言う理論があり、五行とは木・火・土・金・水=肝臓・心臓・脾臓・肺臓・腎臓とそれぞれに対応しており、下図の五行相生相剋図のように5つの要素が循環しています。5つの内臓の運動を紹介した後でまとめとして下図の詳しい説明を致します。

上図を簡易的にいうと、健康・養生に関することは黒→の順に循環します。
起点はどこでもいいのですが、今回は肝(木)の運動を紹介します。
実技1肝臓(木)の運動

①:息をゆっくり吐きながら両脇を閉じ、両肘を軽く脇腹に付けます。
ポイント:肋骨が閉じて肝臓が縮むイメージ
②:息をゆっくり吸いながら両手を左右に指先まで伸ばす。
ポイント:肋骨が開き、手がどこまでも伸びる、また肝臓が伸びるイメージ
③:①②の繰り返し、10~20回くらい行ってください。
注意:体に痛みとかだるさが出るくらいやるのは逆効果です。
※上の写真のように肝臓は左右横方向に伸ばしたり、縮めたりするだけで活性化されます。興味のある方は人体の肝臓の位置を確認してください。ポイントで書いたイメージで動かすことがとても重要です。
また、内臓の運動は毎日負荷をかけずにコツコツとやることが重要です。
★簡単な姿勢をとるだけで内臓とコンタクトできますね、これらのことを知っておくと広い範囲で応用ができますし、紹介する5つの運動を組み合わせて行うと効果は絶大ですよ。
▼肝臓の主な機能
胆汁の作成、炭水化物の交代、タンパク質の交代、脂肪の交代、解毒作用、糖分の貯蔵、血液の貯蔵、ビタミンの貯蔵、体温の発生
▼肝臓に関係する症状→肝臓のストレスのサイン
①筋肉がびくびくする
②足がつる、こむら返り
③手足のしびれ感
④爪がもろくなる、二枚爪
⑤目の充血、眼精疲労
⑥目が疲れやすくかすむ
⑦歯ぎしり、歯肉炎
⑧うっ血症、貧血
⑨飲み過ぎ(アルコール)
⑩ヒステリー身体症状
⑪憂鬱、ふさぎこみ
⑫腰痛
▼肝臓が病むと→五行配当表より
| 1.病気が悪化しやすい季節 | 春(肝機能が乱れやすくなる) |
| 2.病むときの肌や顔色 | 青 |
| 3.病気の時の味の好み | 酸 |
| 4.酸味の働き | 収(筋肉を引き締める作用) |
| 5.体臭や排泄物の臭い | あぶら臭い |
| 6.臓の司る器官 | 筋 |
| 7.病気が現れやすいところ | 目(充血しやすくなる) |
| 8.臓が弱ったとき症状が出やすい所 | 爪(縦じわが出る、もろくなる) |
| 9.臓の病変の現れ | 握(興奮気味に手を握り締める) |
| 10.臓が病んだとき見られる病変 | 語(強い口調でよくしゃべる) |
| 11.臓が病んだ時の分泌液 | 涙(たまる) |
| 12.臓が病んだ時の脈状 | 弦(弓の弦を張ったような脈) |
| 13.臓が病んだ時の感情変化 | 怒(怒りやすい) |
| 14.病気になりやすい気候 | 風(春の風が強い時期) |
| 15.臓の司る精神作用 | 魂 |
| 16.臓を補う果物 | 李(すもも) |
| 17.臓を補う野菜 | 韮(にら) |
| 18.臓を補う穀物 | 麦 |
| 19.臓を補う肉 | 鶏 |
★バックナンバーはコチラ