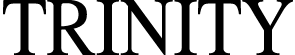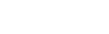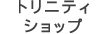不世出の推理作家・江戸川乱歩の71年間の激動の生涯を姓名判断で追う
先日、浅草寺の“四万六千日参り”に足を運びました。
7月9・10日の二日間にお参りすると、4万6千日通い続けて参拝したに等しい功徳を得られるという、大変にご利益の強い祭りの日です。
『TRINITY』の読者の皆様にも、行かれた方がいらっしゃるのではないでしょうか。
雷門の辺りを歩くと、国籍を問わず無数に行き交う人々の、“生”の息吹を感じます。
ノスタルヂアと、エキゾチシズムと、ジャパネスクの交差点とも言うべきあの空気感が、たまらなく好きです。
私と同じく、かつて地方から上京し、下町・浅草をこよなく愛した推理作家がいました。
三島由紀夫、太宰治、森鴎外を取り上げた前3回は純文学の文豪を取り上げたましたが、今回は趣向を変え、今月で没後52年を迎える、日本の推理小説の地平を切り拓いた巨人・江戸川乱歩の71年の軌跡を、姓名判断の観点から追ってみたいと思います。
早稲田大学を卒業後、貿易会社社員を皮切りに古本屋、支那そば屋と多くの職業を経験した乱歩。
小説家としては大正12年、29歳の時に『新青年』に掲載された『二銭銅貨』で、遅咲きのスタートを切りました。
戦後は評論や探偵小説誌『宝石』の編集、“江戸川乱歩賞”の制定そして後進の発掘に尽力し“大乱歩”と謳われ、推理小説という、文学の傍流にあったジャンルをメインストリームに押し上げた、その旺盛な活動の裏には、どんな思いがあったのでしょうか。
筆名“江戸川乱歩”と本名“平井太郎”を対比してみましょう。
筆名・本名共に人格を構成する画数がそれぞれ「3系数」「4系数」で人格大凶相―人気作家の名声と男色趣味のはざまで
筆名『江戸川乱歩』は人格16、外格18、地格20、総画34。基本的な性格と30歳~50歳の運勢を表す人格の16は“チャーミングで神経が細やか、人柄の良さ、情の厚さで成功を収める”大吉数。数え30歳でデビュー、以来、終戦を迎える50歳過ぎまで、明智小五郎と少年探偵団が活躍する『怪人二十面相』ほかヒット作を連発するなど、まさに推理小説の第一人者として栄光を恣(ほしいまま)にしました。そして恋愛運、金運を支配する地格の20は“人柄は良いが心のどこかで他人を信用しない、自己陶酔で意地を張りやすい破壊数”ですが、一般人には大凶でも芸術家には吉に転じます。両性愛者で男色趣味があり、衆道の少年愛や女装、人形愛にサディズム・グロテスクな趣向に強い関心を示した乱歩でしたが、彼はそれを長期に亘る創作活動の中で見事に活かし切りました。一般人としては他人に公表するのを憚る性癖を、見事に芸術へと昇華させた成功例と言えましょう。
人間関係を支配する外格の18は高いプライドを持ち、強い意志でリーダーシップをとる吉数です。戦後は後進の台頭を感じ取ると創作の第一線から退き、いち早く評論活動に転じたのは、その高いプライドと自身の美学故だったからでしょうか。晩年を支配する総画の34は精神主義的な面が強調され、他人の意見に耳を貸さない人が多いという特徴があります。やはり一般的には凶となりますが、集中して作品制作に取り組む芸術家には、吉に転じる数と言えるでしょう。ただ、乱歩は本来、探偵小説の本道とも言うべき本格派を志向していましたが、実際に大衆に熱狂的な支持を得たのは『鏡地獄』『赤い部屋』『人間椅子』といった作品に代表される“変格もの”の通俗スリラーであり、その内心では、忸怩たる思いがあったのではないでしょうか。
一方、本名『平井太郎』は人格8、外格19、地格18、総画27。やはり、人間関係を支配する外格の大凶数・19に注目です。中学時代、当時既に自覚していた男色趣味と相俟って、彼の人間関係の構築に影を落としていた部分が大きかったと推察されます。更に注目すべきは、前回取り上げた森鴎外と同じく、筆名・本名ともに人格を構成する姓の最後と名の最初の画数が同じ系統の画数で、人格が大凶相となっていること。ここが大凶相だと、仕事が順調の時は家庭に波乱が起き、逆に家庭が順境にあると仕事に悪影響が出るなど、常に心労を抱えたり、或いは周囲の人間に心配をかけたりというケースが多いと言えます。乱歩は25歳で結婚、一人息子(平井隆太郎/のち立教大学教授)にも恵まれましたが、生涯、その同性愛趣向は変わることなく、お稚児趣味で若手歌舞伎役者と肉体関係を持ったと伝えられています。家族の心情は、如何ばかりであったでしょうか。