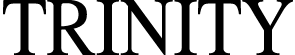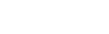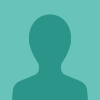「薬葉さんだね。」
そう言って長老がちゃの話の続きを促した。
「はい。」
ちゃは、こんなに長く話をするのは初めてできちんと伝えられるか心配だと思いつつ、伝えずにはいられない気がして言葉を続ける。
「初夏に生まれたばかりだったわたしは、薬葉さんにはそのとき初めて会いました。
薬葉さんはわたしを両手の掌で抱きあげると、心の声でわたしに話しかけてくださいました。
名前を告げるのが精一杯で、からだは動けなくなくなって、目も見えなくなって、体から魂は出ていたかもしれなくて。そのあとは少しの間、薬葉さんと居ました……。」
ちゃは、僅かながらでも自分の記憶を取り戻した事に動揺していた。

甚六は取り戻した記憶のかけらを
ジグソーパズルをはめこむように言葉を紡いだ。
「そうだ。『ちゃ』だよ。薬葉さんは『タチバナ(橘)』と呼んでたけどね。あのときと同じだよぅ。グラさんがわたしに『ちゃ』を預けたように、あの後、薬葉さんの術で式(式神)にした仔猫の魂をこのわたしに預けたんだ。……元々はわたしは薬葉さんの使いで、薬葉さんから子の正国さまに引き継がれていたようだ。わたしはカガミかサガミと呼ばれていたような……。」
甚六は『ちゃ』との1100年前の出会いだけは思い出した。
長老は『ちゃ』を労うように撫でると、ちゃの額に再び九曜の紋がポーッと光を帯びるように浮き出て消えた。
「九曜星……九曜紋。大陸由来の道教や仏教が日本で古い神祭りと混ざって妙見信仰と八幡信仰になったものさ。
仔猫の橘の魂は薬葉殿の術で『式』になり、さらに妙見さまの使い役になる事で魂が冥土に行かずに、この世で将門様をお守りする使命を頂いたのだね。
なぜまだ仔猫だった橘をと言うと、短い期間であっても将門さまや奥方に愛された仔猫だったから、その思いで繋がった将門さまのお側に居られるんだよ。
怒りと悲しみで荒れた将門さまには、魂だけになった橘の姿は認識出来なかったようだがね。
すでにこの頃、将門さまには《強い神通力の有る人間は、平将門に味方として近づけば滅ぶ》という呪詛・祈祷が敵から十重二十重に仕掛けられていた。
そのせいで強い霊能力を持つ薬葉殿や正国さまは将門さまに近づけない。舟小屋の惨状を見て薬葉殿はとっさに橘を妙見様のお力の取次役にした。
そして橘の教育係には正国殿の送った狐を選んだ。甚六のことだね。このとき甚六も薬葉殿から九曜紋を頂いた。」
長老は1100年も前の出来事を、当事者より詳しく解説するが誰もそれに言及しない。
「グラウさんは? この時はまだ出会っていないの?」
観衆の中から小野照崎神社の狐が声をあげた。
「ヴィジョンで見せて。グラウさん。」
その言葉が終わらぬうちに、観衆たちの魂には、低くなだらかな山を北と西に見る、坂東の平地が写り込んできていた。
グラウが妖しく輝き時間に潜る。
祠に集う眷族たちは、時の記憶に魂を委ねる。