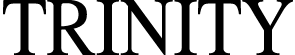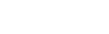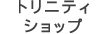第9回 夏目漱石の不思議探索
「不思議、怪談、心霊学に興味があった夏目漱石の探索」
シリアスな人間間の葛藤をリアルに描いた明治の大文豪夏目漱石(1867-1916)もまた、不思議世界の探索者でした。
漱石は、寄席好きで寄席に通って落語や講談をたくさん聞いています。当時の落語界は、第1回・第3回に登場した三遊亭円朝(1839-1900)―笑話であった落語を芸術に高めた円朝の活躍した時代から、彼の弟子たちの時代へと移っていました。弟子の初代三遊亭円遊のように立って踊る芸や四代目立川談志のようにパントマイムで笑わせるような芸が受けたりして、落語は再び軽いお笑い芸の方が主流となりつつありました。
もちろん、漱石のような文豪はそのような芸ではなく、円朝のような芸術的な話芸にひかれました。円朝は近代小説にも通じるような様々な人情噺を創作しますが、中でも怪談噺はとくに有名で、創作デビュー作『真景累ケ淵』、坪内逍遥や二葉亭四迷に影響を与え近代小説の元となった『怪談牡丹灯籠』、『怪談乳房榎』など優れた作品があります。一方、講談の方でも、『百猫伝』という化け猫講談のシリーズで有名な初代桃川如燕(1832-1898)が明治前中期に活躍し、講談界トップで創作力に富み、落語の円朝と並び称された松林伯円(1832-1905)も化猫話や不思議話を語っておりました。
そういうこともあってあの有名な『吾が輩は猫である』(1905-1907)というユーモア風刺小説に登場する猫も、海外の猫の不思議物語の影響も受けているものの、日本の化猫からの影響も受けて書かれている事は作品中にも記されています。
並行して書かれた短編集『樣虚集(ようきょしゅう)』(1906)も留学したイギリスで大流行していた心霊学の影響が濃厚で、神秘現象に憧れる漱石と近代科学の視点を信奉したい漱石の価値観のせめぎあいが見られます。『樣虚集』には、かつての政治犯の監獄であり処刑場であった倫敦塔の亡霊を幻視する紀行文『倫敦塔』(1905)、日露戦争で出征した夫の元へ病気で亡くなった妻の幽霊が訪問してくる話を聞いて、病気の婚約者の事が不安になるが何事もなく無事であったという価値観のせめぎあいそのもののような『琴のそら音』(1905)、お互いの先祖が好意を抱きあった異性の子孫がまた惹かれあうという『趣味の遺伝』(1906)、などの不思議な現象が描かれた作品が収められています。
続いて『夢十夜』(1908)では、殺した男が自分の子供に転生する「六部殺し」の影響が濃厚な「第三夜」は、子供が石のように重くなるという点で『ゲゲゲの鬼太郎』で有名な子泣き爺にも似ています。
このように見てくると漱石がリアルに人間の葛藤を描いた作品にしても、その裏面には、神秘や霊的な事象、前世の因縁などが隠れているようにも思えてきます。例えば、『草枕』(1906)の変幻自在な奈美、『虞美人草』(1907)の我が強く才気走った女藤尾、『それから』(1909)の代助の無謀とも思われる出奔、後の『こころ』(1914)の先生を追い詰めてゆく何か、もしかしたらそれはよく言われるように自我、倫理意識、罪意識、道徳心などではなく、実は、神秘的なる何か、前世・現世の因縁、霊的なる何かなのかもしれません。
そして、漱石は、臨死体験をする事になるのです(『思い出すことなど』1910)。『新・あの世はあった』では、この漱石の臨死体験を、様々な臨死体験の記録と比較しています。
夏目漱石『吾輩は猫である』
夏目漱石『倫敦塔・幻影の盾』(『樣虚集』)
夏目漱石『夢十夜』
夏目漱石『思い出すことなど』
三浦正雄著『新・あの世はあった』